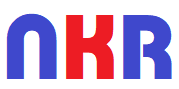北朝鮮女性の怒りを爆発させた、ある「DV夫」たちの勘違い
朝鮮半島が日本の植民地支配下にあった1920年代、中高等教育を受けた女性たちは、「新女性」と呼ばれ、社会への進出を果たしていった。その背景にあったのは、思想家・平塚らいてう(ひらつか・らいちょう)の新婦人協会の活動だ。その立ち上げに関わった奥むめおの夫である中西伊之助は、平壌日報や平壌日日新聞で記者として活動し、投獄も経験している。
奥と中西の両人は1925年8月、ソウルで講演会を開くなど、女性運動、労働運動に限らず、被差別階級の白丁(ペクチョン)の解放を目指した衡平社や、朴烈・金子文子夫妻とも交流するなど、朝鮮における様々な社会運動に影響を与えた。
植民地支配下から解放された後の1946年7月30日、世界人権宣言が国連総会で採択される2年前に、現在の北朝鮮政府の前身である北朝鮮臨時人民委員会は、「男女平等権法令」を制定する。女性選挙権、被選挙権、男女同一賃金、結婚の自由、離婚の権利、一夫多妻制の禁止、相続権などを定めた、当時としては世界的に見ても非常に進んだ法律だった。
それから七十数年。北朝鮮政府は「女性が良き母、良き妻であることは社会主義の美徳である」と宣伝するなど、ジェンダー政策の思想面において大きな後退が見られるようになった。一方で、過去30年の間になし崩し的に進んだ市場経済化は、組織生活から相対的に自由な女性を、経済活動への主体へと押し上げた。女性の社会的地位や女性を巡る社会の意識は低いままだが、経済における女性の地位は高いという歪な状態を生み出したのだ。(参考記事:北朝鮮で見捨てられる「小言の多い退職後の夫」)
「男のおかげ」
そうした状況は、男女間の習慣にも現れている。